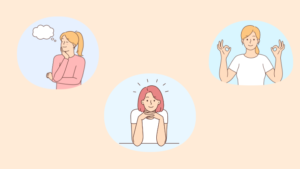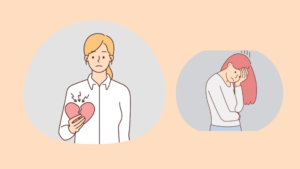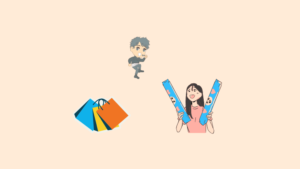推し活は、ややわかりにくい言葉で説明されることが多いです。
そこで、推し活に関する用語を解説したいと思います。
「推し活」の周辺領域と思われる「オタ活」分野も少々含んでおります。
情報収集元は、サブカルチャーに詳しい専門家です。
周りに迷惑をかけたくないので専門家の名前も匿名にさせていただいております。
私が初めて「推し活」らしいことをしたのは30年以上前。
昔も今も、スターではない男性を応援しています。
推し(おし)
「推し」とは、応援している人物やキャラクターのことを指します。
実在の人物、架空の人物、歴史上の人物のほか、建物、乗り物といった無生物も「推し」の対象です。
「推し」は、具体的には、特に、アイドルや俳優、声優、アニメキャラクターなどを指すことが多いです。
「推し」は単に好きという感情だけでなく、その人物やキャラクターに対して深い愛情や尊敬を抱いていることを示す言葉でもあります。
推し活(おしかつ)
「推し活」は、推しを応援するための活動のことを指します。
具体的には、ライブに参加したり、グッズを集めたり、SNSで推しについて話したりといった行動があります。
他にも、推しにちなんだ料理を作る、勝手に誕生日を祝うなど、推しに関係するあらゆる行動は「推し活」と言えます。
「推し活」は、単なる趣味ではなく、推しを応援するために時間やお金をかける「情熱的な活動」と、とらえられています。
オタク(おたく)
「オタク」は、特定の趣味や興味に対して非常に熱中している人を指す言葉です。
特に、アニメ、マンガ、ゲーム、アイドル、声優などに対して強い愛情を持ち、知識が豊富であることが特徴です。
以前は軽蔑的な意味合いもありましたが、近年では自分の趣味について博識な人というポジティブな意味合いが前に出てきています。
オタ活(おたかつ)
「オタ活」は、「オタク活動」の略で、自分の趣味や興味を深めたり、コミュニティで交流を楽しんだりする活動全般を指します。
例えば、アニメの視聴、マンガの購読、同じ趣味を持つ人々とのネット交流などがオタ活に該当します。
オタ活は、推し活と近い部分もありますが、必ずしも推しがいるわけではなく、もっと広範囲な活動を指すことが多いです。
ヲタ活(をたかつ)
「ヲタ活」は、「オタ活」とほぼ同じ意味ですが、書き方が「ヲタク」の「ヲ」に変わっています。
これは、昔からのオタク文化における独特の表記方法であり、特にオタクの人々が自分たちを強調するために使うことがあります。
「オタ活」と「ヲタ活」は基本的に意味は同じですが、「ヲタ活」はより個性的な表現です。
同担(どうたん)
「同担」は、推しが同じであるファンを指します。
自分と同じ推しを応援している人を意味します。
例えば、同じアイドルやアーティストを推しているファン同士が「同担」と呼ばれることがあります。
語源は「同じ担当」という言葉です。
元々は「グループのファン」の中で、そのメンバーの誰が好き、誰が推し・・という話になり、同じメンバーが好きなら「同担」と言われるようになりました。
そこから転じて、現在では、広く、同じ有名人、同じタレントが好きなら、その有名人やタレントがピン(一人)で活動中であっても「同担」と表現するようになりつつあります。
同担拒否(どうたんきょひ)
「同担拒否」は、同じ推しを応援しているファンとの関係を避けたいという気持ちを表します。
つまり、他のファンと自分の推しの情報を共有したくない、あるいは他のファンの推し方が自分と合わないと感じて距離を置く場合に使います。
これは、特にアイドルやアーティストのファンコミュニティで見られる現象と言えます。
同担が全部目の前からいなくなれば良いという意味ではなく、身近での関わり合いを避けたいという気持ちや行動を意味しています。
箱推し(はこおし)
「箱推し」は、特定のグループやユニット全体を応援することを指します。
例えば、アイドルグループのすべてのメンバーを応援している場合、「箱推し」と呼ばれます。
特定のメンバーではなく、グループやユニット全体を好きな場合に使われる言葉です。
推しメン(おしめん)
「推しメン」は、「推し」と「メンバー」を組み合わせた言葉で、特にアイドルやグループ活動をしているアーティストの中で、自分が特に好きで応援しているメンバーを指します。
例えば、アイドルグループの中で特定の一人に特に思い入れがあり、その人を推している場合に「私の推しメンは〇〇さんです」というように使います。
ガチ(がち)
「ガチ」は「本気」や「真剣」を意味する俗語で、何かに対して全力で取り組む様子を表します。「ガチで〇〇」という形で、強調表現としても使われます。
「ガチ」は推し活だけでなく、日常会話や他の趣味の文脈でも使われます。
ガチ推し(がちおし)
「ガチ推し」は、「推し」という言葉と「ガチ(本気)」を組み合わせた表現で、「自分が本気で応援している推し」という意味になります。
主に推し活やオタ活で使われる言葉で「推し」に対する情熱の度合いを示します。
ガチ推しは、グッズの購入、イベント参加、SNSでの宣伝など、推しのために多くの時間やお金、エネルギーを注ぐ行動を指します。
「ゆる推し」(後述)や「箱推し」とは異なり、特定の1人(または1グループ)に集中して熱く応援することが特徴です。
ゆる推し(ゆるおし)
「ゆる推し」とは、特定の推しに対して、強い情熱を持つというよりは、緩やかに応援したり、ほどほどの距離感で楽しむスタイルを指します。
いわゆる「ガチ推し」(全力で応援する)の対義語的な存在です。
ゆる推しでは、必ずしもグッズを揃えたりイベントに参加したりする必要はありません。
SNSやテレビなどを通して、自然体で応援します。
応援することが生活の中心ではなく、自分のペースで楽しむことが優先されます。
「箱推し」や「他担推し」(主に応援する推し以外の人を推す)のように、幅広い応援スタイルを持つ人にも使われます。
特定の一人だけに情熱を注ぐわけではない場合に、ゆる推しとして表現することもあります。
ゆる推しは「気軽に応援する」というポジティブな意味合いが強く、「無理しない応援スタイル」として広がっています。
そのため、「推し活」に疲れた人が、ゆる推しに切り替えるケースも多いと言われています。
聖地(せいち)
「聖地」は、ファンにとって特別な意味を持つ場所を指します。
例えば、アニメや映画の舞台になった場所や、特定のアイドルがよく訪れる場所などが聖地とされます。
ファンにとって聖地は、推しとつながりを感じることができる大切な場所です。
聖地巡礼(せいちじゅんれい)
「聖地巡礼」は、アニメや映画、アイドルの活動場所などの「聖地」を実際に訪れることを指します。
これは、ファンが自分の推しに関連する場所を訪れて、聖地と呼ばれる場所で特別な体験をしたり、写真を撮ったりする活動です。
聖地巡礼は、推しとのつながりを感じる方法の一つとして、ファン活動の中でも人気があります。
遠征(えんせい)
「遠征」とは、推しの活動を応援するために、自分が住んでいる地域を離れて遠方まで足を運ぶことを指します。
特に、コンサートや舞台、イベントなど、推しが出演する場所に行く場合によく使われます。
住んでいる場所が東京であっても、大阪や福岡など別の都市でライブが行われる場合に「大阪までライブ遠征します」と言うように使います。
推しが出演する舞台や限定上映の映画が特定の地域でしか見られない場合、「そのために遠征する」という表現もします。
遠征する場合、移動手段(新幹線や飛行機など)や宿泊先を手配し、時には複数日間にわたる旅になることもあります。
「遠征組」という言葉で、遠方から参加するファンを指す場合もあります。
「遠征」には、応援の熱意や情熱が込められている一方で、ファン同士の交流の中では「遠征するのはすごい!」という一種のリスペクトを含むこともあります。
経済的・時間的なハードルがあるため、遠征自体が「熱心なファン」の象徴と見られることもあります。
推しごと(おしごと)
「推しごと」は、「推しを応援するための活動全般」や「推しを支えるために自分が行う努力」を意味する言葉です。
具体例としては、 推し活に必要な資金を得るために仕事を頑張ること、イベントや公演のチケットを入手するための準備や努力をすること、ファンアートやファンレターを作成することです。
「推しごと」は、単なる趣味を超えて、自分の生活の一部として推しを応援することを示します。
「推しごと」は、推しに向けた活動を「楽しむ」だけでなく、「頑張る」姿勢を強調します。
「推しごと」は、推し活を日常生活の中で優先する姿勢を象徴する言葉です。
近年、推し活の多様化に伴い、SNSやファンコミュニティでこの言葉が頻繁に使われるようになったと言えます。
出待ち(でまち)
「出待ち」とは、イベントや公演の終了後に、出演者が会場から出てくるのを待ち、直接応援や交流を試みる行為を指します。
出待ちが可能なジャンルとしては、舞台やライブが挙げられましたが、最近は、セキュリティーやプライバシーへの配慮から出待ちを禁止する場合が非常に多くなっています。
出待ちが制限されているにもかかわらず出待ちをすると、違法行為やトラブルにも発展しやすいので注意が必要とされています。